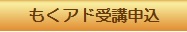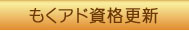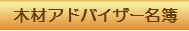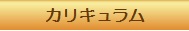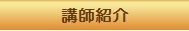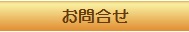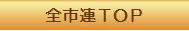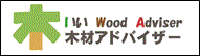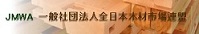|
日本は世界有数の森林国であり、森林は様々な働きを通じて私たちの暮らしを支えています。 いま私たちにとって、増加を続ける国内の森林資源の有効利用を進め、後継の森林を健全に育成していくことが大切です。 また私たちは、CO2を固定している木材を住宅や家具、都市建築等に使うことにより、地球温暖化防止に貢献できるほか、風土に適した木材を利用して建てた家は丈夫で、しかも木材の調湿作用は住む人の健康を守る働きがあるなど、木材利用は様々な効用をもたらすものです。 政府は、国産材の利用を拡大し林業・木材産業の活性化を図るため、平成21年に「森林・林業再生プラン」を策定し、さらに平成22年10月には、国等の公共建築物等の木造化、木質化を進める「公共建築物等への木材の利用の促進に関する法律」を施行しました。 これらの着実な推進のためには、木材業界としても品質・性能の確かな製品の供給のほか、木材に関する情報を工務店、設計者等木造建築に関わる方々に提供していくことが大切です。しかしながら環境問題や木材需給、日本の林業の現状、木の性質、木造建築に関する知識を体系的に学ぶ機会は少なく、木材や木材利用について適切な助言ができる人材が不足しており、その育成が急がれておりました。 全日本木材市場連盟は、これまで木材利用のPRや品質規格の明確な木材の利用拡大等に取り組んで参りましたが、平成23年度から新たに木材や木材利用の助言・指導ができる人材を養成し「木材アドバイザー」として認定し、その任に当たっていただく制度を創設いたしました。この制度は、東京木材市場協会(会長 市川英治)が、平成22年度に実施した人材養成事業を引き継いでおります。また、制度の企画運営は、森林・林業、木材、建築などの分野で、それぞれ第一人者の先生にご協力頂いております。 全市連といたしましては、制度の一層の充実を図るとともに「木材アドバイザー」の活動が社会的にも高い評価を受け、その活用が促進されるよう努力して参る所存です。これまでご支援、ご協力を頂いた関係各位に感謝申し上げますとともに、引き続きのご指導、ご協力をお願い申し上げます。 |
|
平成25年6月1日 一般社団法人全日本木材市場連盟 会長 市川 英治 |
|
日本は自然環境に恵まれ、森林が国土の大半を占める森林国であり、古くから木材を利用して気候風土に合わせた家づくりやまちづくりを行ってきました。森林は木材を供給するだけでなく、国土保全、水源のかん養、二酸化炭素の固定による地球温暖化防止、生物多様性の保全への貢献などを通じて私たちの暮らしを支えています。 近年は、木造建築が炭素固定によって地球温暖化対策に貢献することにも国民の理解が深まってきました。SHK制度(温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度)の対象に森林のCO2吸収量と木材製品の炭素固定量が追加されることとなりました。SDGs(持続可能な開発目標)や温暖化対策の目標2050年ネット・ゼロ(カーボンニュートラル)を実現するうえで、建築用材などの木材利用を促進し、木材の価値を高め、再造林を推進し、森林資源の循環利用を推進することがますます重要になってきています。 令和3年に「都市の木造化推進法」が施行され、中高層建築物においても木材利用が進んでいます。学校などの公共建築物、商業施設や社屋などに木造建築が採用されるようになり、木材の構造や内装を見せる多くの建築物が建てられるようになりました。木材を使うことが評価される時代になったと感じています。このような変化の中で、木材アドバイザーの役割はますます重要になっております。 木材アドバイザー養成講習会は、森林・林業、木材、建築などの分野の第一人者の先生方に講師としてご協力いただいております。長年にわたりこの制度の実施にご協力いただいておりますことに改めて感謝申し上げます。この度、講師の皆様に「講義のねらいと木材アドバイザーへの期待」を取りまとめていただきましたのでご紹介いたします。 平成23年の開始以来、毎年、およそ80名の方が講習会を受講され、多くの方々が木材利用の第一線で活躍しておられます。全日本木材市場連盟といたしましては、制度の一層の充実を図り、時代の要請に応えられるよう引き続き努力してまいる所存です。これまでご支援、ご協力いただいた関係各位に感謝申し上げますとともに、引き続きのご指導、ご協力をお願い申し上げます。 |
|
令和7年10月1日 一般社団法人 全日本木材市場連盟 会 長 守 屋 長 光 |
地球環境保全と森林・木材利用平塚 基志 早稲田大学教授木材は私たちの生活に欠かせないものであり、同時に木材が生産される森林生態系にはCO2吸収機能、水源涵養機能、土砂流出防止機能といった多面的機能があります。したがって、多面的機能がバランスよく調和し、森林生態系を捉えていくことが求められます。講義ではそうした点に触れます。 森林と人との関わり・日本の林業とその課題赤堀 楠雄 林材ライター森林・林業について知るには現場に足を運ぶことが最善だと考えています。例えば森づくりについては、一般的な手法や政策的に推奨されている手法もありますが、現場はひとつとして同じものはなく、そこで実践されていることは非常に多様です。型にはまった知識では木材アドバイザーは務まりません。講義では、幅広い視野を養っていただけるような内容を用意します。現場から答えを得る姿勢を身に付けてください。 木材需給の動向と木材産業遠藤 日雄 NPO法人活木活木森ネットワーク理事長木材アドバイザー養成講習会は、開講以来人気を博しています。年々同じような内容ではなく、例えば、今年度の講義は、トランプ政権の対カナダ重価税が、日本の森林・林業・木材産業にどのような影響を与えるのか? 日本はなにをすべきなのか?東京、大阪会場でいっしょに考えていきたいと思います。ご期待ください。 木材の構造と性質−知っておくべき基本的なことがらとルーペによる木材の観察杉山 淳司 京都大学名誉教授木材は、調湿性・断熱性・加工のしやすさ・軽さなどに加え、かつて短所とされた異方性や可燃性、生分解性までもが、近年ではカーボンニュートラルの観点から再評価されています。こうした木材を適切に活用するには、その特性や生物学的な起源を正しく理解することが欠かせません。本講座では、木材の基本的な特徴や分類の考え方を、実物を見ながらわかりやすく学び、業務に活かせる知識を身につけていただきます。 木造建築・木造住宅に使う木質材料大橋 好光 東京都市大学名誉教授「木造建築・木造住宅に使う木質材料」では、建築側が求めている木材の物性と、それがどのように決められ、運用されているかを解説します。建築に使う木材には、強さと剛さが求められますが、木材は強度のバラツキが大きく、また含水率や荷重継続の影響を受けます。これらの扱いを解説します。更に、集成材、CLT、合板などのエンジニアリングウッドについて、その構造的な特徴と扱い方を解説します。 木造建築と木造住宅栗田紀之 建築環境ワークス協同組合(A/E WORKS)専務理事「木造建築と木造住宅」は建築分野での2つ目の講習になります。木造建築について基本的な知見を得ていただきたく、大きく3つの内容を講習します。まず「木造建築の構造形式」です。特に軸組構法と枠組壁工法のアウトラインを解説します。次に「木造建築と耐震・耐風」で、木造建築の構造安全性について概説します。そのうち小規模の木造住宅等で用いられる壁量計算を少し詳しく取り上げます。最後に「木造の耐火」です。近年、中大規模な木造建築が市街地にも建てられていますが、構造のみならず耐火がカギになっています。 |